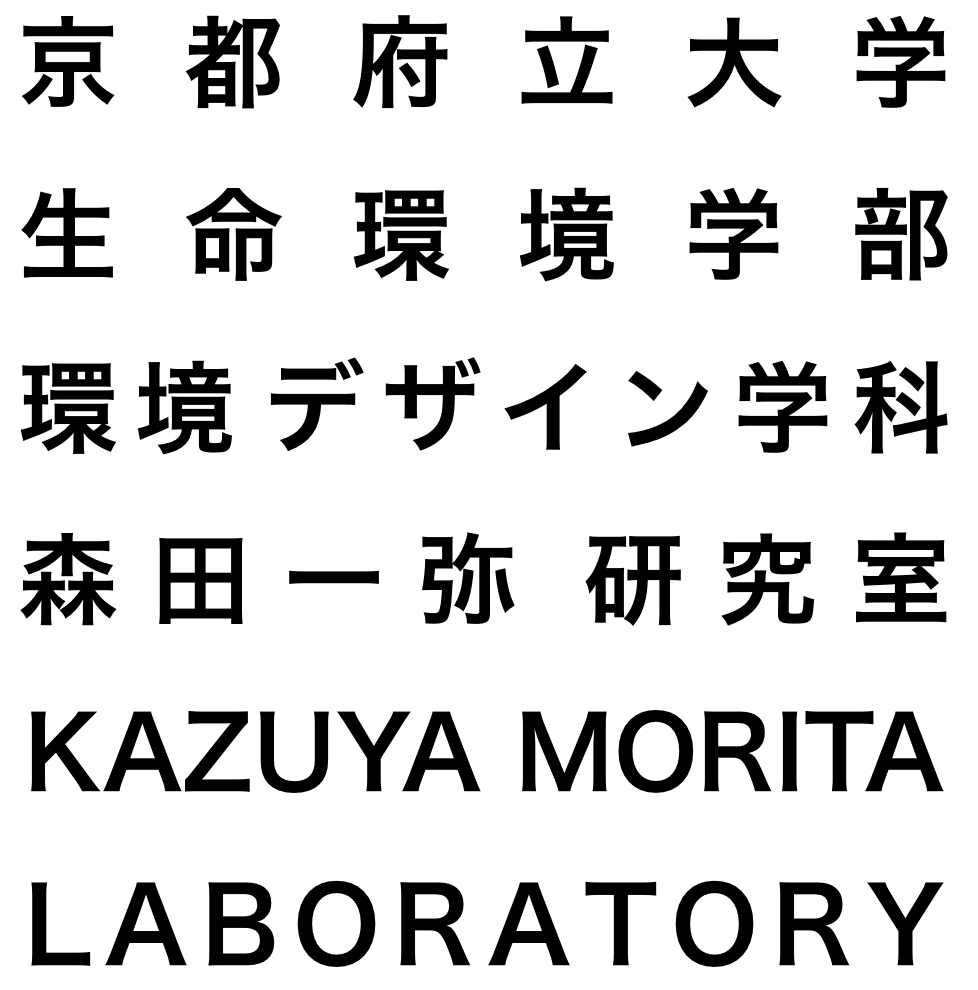レクチャー特別版|渡辺菊眞
話し手
渡辺菊眞 〈高知工科大学 准教授 / D環境造形システム研究所所長〉
司会
𩵋谷繁礼〈京都工芸繊維大学 特任教授 / 𩵋谷繁礼建築研究所〉
森田 一弥〈京都府立大学 准教授 / 森田一弥建築設計事務所〉
―
はじめに
森田――
そろそろ時間になりましたので、講演会を始めたいと思います。会を企画した1人である𩵋谷さんからまずは会の趣旨説明をさせていただきます。
𩵋谷――
京都工芸繊維大学の𩵋谷です。今日は渡辺菊眞さんの「地域-地球型建築を語る」楽しみにしています。通常、博士論文の公聴会っていうものは、結構閉じたところがあって、そんなに公開されずに終わってしまうことが多い。それじゃあ、もったいないんじゃないかっていうようなことを薄々思っていて。
6、7年前に、山崎泰寛さんと満田衛資さんがちょうど同じ時期に、D論を書かれたので、岡田栄造さん、今九州大学で教鞭取られていますけども、岡田さんがその時、2人の発表を聞こうという会をやったのが1番最初です。当時はなんか寒くて広い場所で、お酒を飲みながらの会だったんですね。で、誰も聞いてない。そういうこともありながら、その次に今回企画してくださった森田一弥さんのD論の発表会があって、今回が3回目になります。

渡辺菊眞さんは1971年生まれで、奈良県出身、京都大学の工学部卒業、大学院工学研究科修了で、その後博士課程。その時に僕は出会い、研究室で一緒させていただいていました。森田さんは同級生です。個人的には非常に畏怖を抱いておりまして、いろんな意味で。個人的な話なんですけども、特に学生の時もその後もなんですけども、 一緒に建築の本質について話す機会が非常に多く、その中で僕は建築の空間ということだとか、あるいは人間として建築にいかに向き合うかとか、そういうことを学びました。今、非常に大きな影響を受けてます。ですので、今日、とても楽しみにしております。
その後、博士課程の方の単位を満期取得退学されて、現在は高知工科大学で教鞭を取られているのと同時に、D環境造形システム研究所所長で、建築家としても活躍されております。 2024年に博士論文を完成されて、今日発表していただくようお願いしました。大体今日、今から2時間ぐらいお話いただいて、その後、皆さんでざっくばらんに質問時間みたいなことを1時間ほど時間取っております。
では、よろしくお願いいたします。
自己紹介
渡辺――
皆さんどうもこんにちは。こんにちはかこんばんはか微妙な時間になってきましたけども、今ご紹介に預かりました渡辺菊眞と申します。
今日はこのような会を設けてくださって、本当にどうもありがとうございます。 先ほどお話ありましたように、2024年9月に京都工芸繊維大学で、今日も来てくださっているので緊張してるんですが、長坂大先生の指導のもと博士論文を書き上げまして、今日お時間をいただいてるということになっております。 そうですね、先ほどちょっと𩵋谷さんがおっしゃっていたように、マックス5人入るかどうかぐらいの部屋で公聴会がございました。お話をさせていただいたんですが、それはそれで非常にありがたい会でした。今日、こういう場を設けていただいたことで、自身が迷ってきたこととか考えていることをお話できる機会をいただけたことを非常にありがたく思っております。今日はどうもよろしくお願いいたします。

でしたら、早速始めようと思うんですが、今日企画してくださった森田一弥さん、あと𩵋谷繫礼さんなんですが、森田さんは大学の同級生でして、 あんまり本人には言ってないんですけれども、結構恩人的なところが私にはあってですね。 土嚢の建築というのを私やってたんですが、2003年、2004年の頃はそれとどう付き合っていくのかあんまよくわかってなくてですね。なんとなく立ち位置が見えずに悶々としてた時期があったんですが、百万遍の交差点でばったり出会って、お前面白いことやってるじゃないかっていうことを森田さんに言っていただいてですね。
土嚢なんて普通はあんま誰もできへんから、すごい羨ましいものをお前は武器で持ってるんだぞみたいなことを言っていただいて。あ、そうかと思って、僕、土嚢嫌いだったんですけど、そういうこと言ってるんじゃなくって、建築を作り上げる重要な技術として自身で受け止めて、 ちゃんと前向きにやっていこうという気になれたのはその一言だったというのがあります。
あと、今回学位の取得になりましたが、2019年、高知で自分が25年ぐらいやってきたアンビルドのものとか含めた全作品を集めた個展をした時に高知まで来てくださってですね。これ、𩵋谷さんも来てくださったんですが、 その時にこういうものを博士論文にまとめろよってことをおっしゃってくれたのも森田さんだったので、 しょっちゅうお会いしてるわけじゃないんですが、1番なんか節目節目の時にお会いする機会があって、とても重要な一言をかけてくださる同僚であります。
𩵋谷さんは先ほどお話もいただいてたように、 大学時代、年の差みたいなのがあったこともあって夜中2時ぐらいに𩵋谷さんの下宿に行ってお酒でも飲みましょうとか言って無理やり飲んでたんですけれども。それだけだとあんまりなので、当時神社や寺院とか行きまくってた時に、一緒にそこに行って、帰りしな飲む。よくJRのプラットホームとかで飲んていたんですが、そういうことを一緒にずっとやっていただいてて。
𩵋谷さんといた時にすごいなと思ったのが、1995年に阪神淡路大震災があって、 その時にご自身は兵庫県出身なので、あるところ被災的な状況があったということなんですが、腕をこうちょっと揺すってみて、要は地球が、ちょっと表層が揺れただけで、こんなに建物が壊れてしまう。 そういう中で、自身が建築やってるっていうことについて、なんとも言えない。 この程度でゆさゆさしているところで、自分たちはやってるんだなってことを思ったという話をしていただいて、すごいスケール感覚で物事を考えてる方だなっていうのがあります。
それ以降もよくお会いする機会もありますし、19年の高知の展示会にも来てくださってたんで、 またこれまた恩義のある方になります。という2人が企画してくださって大変ありがたく思っておりますので、精一杯頑張りたいと思います。
でしたら、ちょっと座らせていただいて、今から講演を始めたいと思います。レクチャーとしては、「地域-地球型建築を語る」ということですが、何か奇妙なルビをふっています。これについてまた後でお話ししますが、 「すぐこことはるかかなたをつなぐ」ということが地域-地球型建築となってまして、それについてお話しさせていただきます。
まず私の経歴について、そもそも誰やねんっていうことがあると思いますから、簡単に説明をさせていただきます。経歴はこのようなことになるんですが、奈良県に生まれて、大学時代は京都大学で過ごしてます。 2001年に博士の単位を取得して退学してまして、そこから、渡辺豊和建築工房っていうアトリエ事務所に勤務して、その後に2007年に独立してます。独立した直後の2009年から高知工科大学に赴任しまして、現職です。そこで環境研究デザイン研究室という研究室の代表を務めています。

今赤字で書いた経歴のことを少し補足しますと、この研究は実はサブタイトルがパッシブシステムの導入とフィールドの読解を通してとなってるんですが、京都大学時代は要はフィールドの読解をやる研究室におりました。
僕自身は京都の周辺部・山の辺というあたり、特に東山の方をやってたんですが、古代の葬送地っていうところがフィールドです。 明治以降になりますとあまり人が住んでなかったところが、都市の拡大に伴って居住地化していくっていう時に、やはり昔から葬送地であるという恐れ多いところに住むというのは簡単なことじゃないので、ある種葛藤とかがありながら、そこを少しずつ畏怖を抱きながら住みこなしていく過程というのがあります。そういったことが空間の特質でどう現れるのかっていうことについて研究をしていました。 1つ査読論文を書き上げた時に、大学の方を退学しています。
その後、アトリエ事務所に勤めているんですが、その時に出向という形で山形県にある太陽建築研究所という井山武司さんが主催されてるところに住み込みで出ていきまして、そこでパッシブソーラーシステムの共同研究をしています。 半年ぐらいだったんですが、井山さんしかいないところに僕1人だったので、この左側の写真、特に全く2人っきりでパッシンブのことを研究したということがありますので、右にある太陽建築という書籍は、これは井山さんの遺稿なんですが、お亡くなりになった時に 出版できずに残ってた原稿なんですけれども、そういった縁もありましたので、私が編集して書籍化しています。

あと他にはですね、大学を出てからすぐ、世界の各地の被災地だとか貧困地で、国際協力としての建築実践活動というのをいくつかやってきています。ここでやってきたことも、今回の論文の方に収録しています。高知工科大学に着任してからはですね、環境建築デザイン研究室という新しい研究室を立ち上げて、そこで環境建築という枠組みというものを下にある図のように定めまして、自然環境の適用と文化環境の適用っていうものを横軸において、建築として人にどういう風に響いていくのかっていうのを縦軸に置きながら、全体として環境建築になるんだよっていうことを枠組みを定めて、それを実践的に作りながら教鞭を取っているというような形になります。