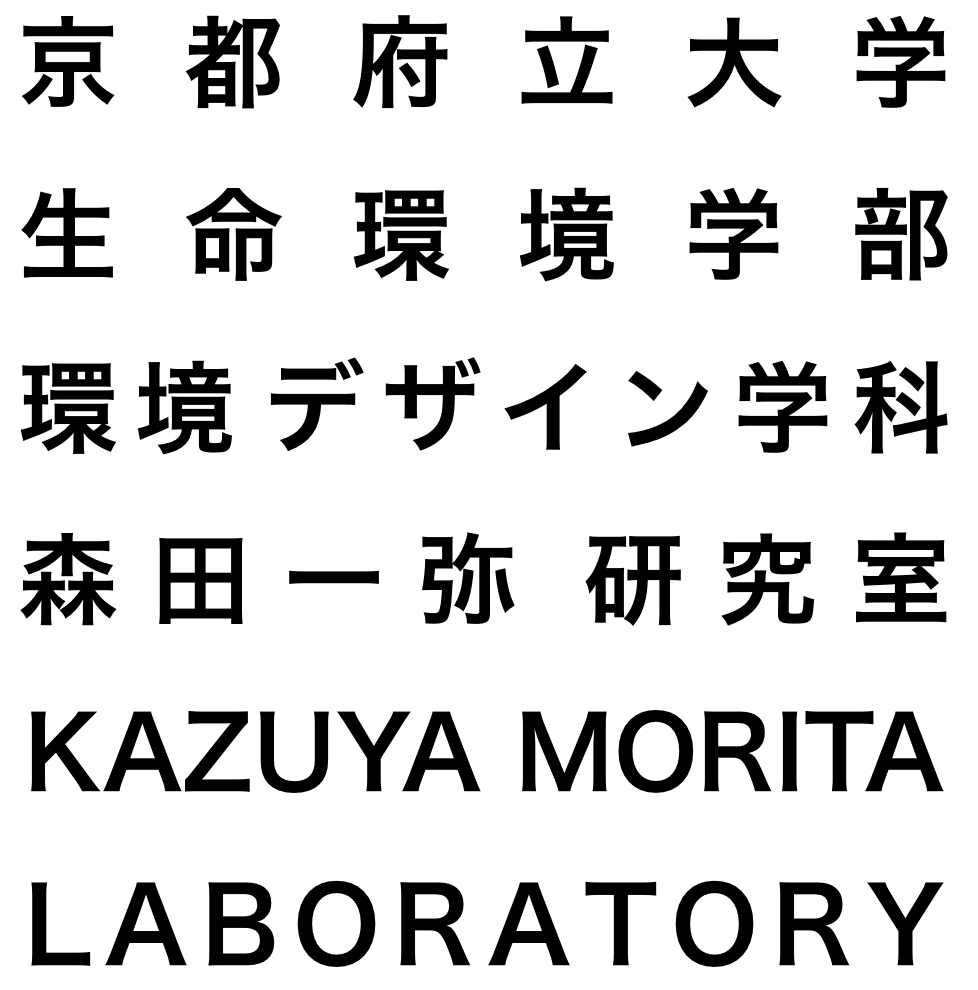汎用と専用
柳室|
次は2つ目の「汎用と専用」という話です。
構造の役割としては、当然、物理的な強度 に関して安全を確保するという話があるんですが、それ以外に変化に対する強度があり、耐久性というよりは建物としてどれぐらい長く使ってもらえるかということです。全てがコントロールできるわけじゃないんですが、ステムとか構造材のレベルであらかじめどれぐらい考えておけるかということを意識しています。

ここにあるようなドミノシステムはこの時代においてはすごく斬新なアイデアで、それまで必要だった壁を取っ払って、「これでどんな平面計画でも建物は作れますよ」というその時代の1つのラディカルな提案だったと思うんです。建築家が関わらないような例えば、マンションとか事務所ビルを作るときに、構造と意匠との一致をあまり意識せずに、そこに仕上げの壁が来ようが来まいがラーメン構造で対応することが経済的で、それが一般的に行われています。建物によってはそのあり方では良くないと思っていて、ラーメン構造に変わる汎用的な状態とはどういうことがあるかを考えながら、設計をしています。

これは木村松本さんたち〈木村松本建築設計事務所〉と共同した作品〈HouseM〉ですが、最初のスケッチの段階で建物の半分が半屋外のような透過性のあるスペースで、残り半分が閉じているスペースというような、そういうラディカルな案でした。


図版 木村松本建築設計事務所
この青い部分に決められた壁を置かずに、右側の範囲だけでなるべく耐力壁を取って対応するということが、1つの方法としてあると思います。一方で、特殊な条件だけに対応できるようなものをあらかじめ用意するというのが、逆に可能性を狭めているんじゃないかという風に思って。

この時は、柱・梁というものを変わらないものとして、それ以外のところを可変的なものとして扱ったら、今回は半分だけが閉じているケースで建物が出来上がりますが、それ以外のケースの時にも成立する建物が型としてできるんじゃないかと思って設計を進めました。柱・梁は鉛直荷重に抵抗する材として変わらないものとしてまずあって、斜材、それから、構造用面材を水平方向の力に抵抗するものとして、状況に合わせて変えていけるような状態で設計をしようと考えました。
一方で構造用合板だと片側 1面貼ることと、筋交いをばってんで入れる状態はおよそ同じような剛性と強度なので、構造的には等価に扱います。意匠的には面材があることと筋交いがあることは光を通すか通さないかということで別の状態になるので、構造的にはアンバランスにならないように計画をして、意匠的には場所によって切り替えていくってことを許容する。そういうことをコントロールしながら設計をしました。
構造設計の特徴として、クライアントから少し距離があるということがあります。意匠設計の方はどうしてもクライアントの直接的な要望に答えないといけない一方で、構造の人は1歩引いてそういうことを提案できるので、汎用性や、普遍性に意識を向けられる存在だと思っています。
提案されているプランに対してアイデアを出すんですけども、別の要望が来た時にどういう状態になるかということも、所内では、「例えばこうなったらどうなる」みたいなことを考えていました。この架構の可能性みたいなことを検証して、アンカーボルトだとか接合部も、使用条件が変わった場合でも対応できるような仕組みをあらかじめ用意しました

森田|
要するに、将来的に壁とかの配置が変わっても大丈夫ということですか。
柳室|
そうです。だから、ブレースの位置を変えたり耐力壁の位置を変えたりしても大丈夫なように設計をしてます。もしこの建物を別の人が購入して、あるいは、次の世代に引き継いだ時に、比較的改修をやりやすい状態でスタートできるということがあります。
あらかじめいくつかの可能性を考えておくというのが、ある特定のクライアントに対して答えを出す時に、それ以外の多くの人、あるいは新しい建築を作るという意味において貢献度が高まるんじゃないかなと。
森田|
ちょっと余裕を見てるってことですよね、ギリギリの設計にせずに。
柳室|
接合部の位置に関してはそうですね。この時にはいらないところにアンカーボルトを入れてるんですが、設計する時に全てをギリギリで設計するっていうのはないです。例えば、非対称だったりしたら対称になるように配置したり、そういうのはやるようにしています。そういうことをプラスアルファで設計していって、「もし位置が変わったとしたらどうか」みたいなことを、イメージするんですよ。
その時にやることは、汎用性の確保に繋がるのかなと。それがそのまま安全率の上昇に繋がっているケースもあるし、そういう時間軸に対する強度みたいなところも増えていると。例えば、これで数百万円変わるレベルであればお施主さんにも相談しなければいけないと思うんですけど、 そうならないレベルで汎用性についてあらかじめ付加しているという状態です。
RCの改修の設計というのも最近は多いです。実現したものはまだ多くないですが、調査まではすることが多くて、そうすると図面がなかったり、計算書がなかったりっていうものが結構多くて。本当にそこにある壁が耐力壁なのか、一見よくわからないものが多くて。すごくやりにくいなと思っています。
RCの建物を建てるとき、特に壁式の建物を作る時は、とりあえず壁を作れるとこはRCの壁で閉じてしまうっていうことが多いかなと。それは仕上げの問題上、RCじゃないものに切り替える方がむしろお金かかってしまう。なので、コンクリートブロックにしようと思っても、なかなかしにくい。
敷地条件としては、出町商店街のとある一角に立っています。片面は全部閉じてるんで、下側が隣地に接してるので全く開口がいらなくて、上側と右側が開口を取れるというような状態です。構造的に言うと、下側と左側をそのまま 閉じてしまうとバランスが悪いので、バランスのことを考えると耐力壁にしない方がい。
あとは、この後にもしかしたらこの敷地の西側に建物が増築されるかもしれない勝手なストーリーを色々と考えて、この建物が最低限必要なものを耐力壁として作って、それ以外のところは明らかにわかるように作ったらどうかってことを考えました。

最初はコンクリートブロックか、ALCの仕上げですることを考えていたんですが、お金かかるというような話があって。耐力壁として見なせるサイズというのが12cm以上なので、 外壁として成立する10cm。配筋のことと考えると10cmあたりが最小ラインなんですが、壁を作りつつ構造のスリットを入れて、改修工事レベルでは穴を開けられるような状態として、非耐力壁の部分も薄いRCの壁で作りました。階段室のところはそうなんですけども、梁があって少し段が落ちて、非耐力壁がついていると。

これがこのプロジェクトのこの瞬間の表情なんですが、もしかしたらこのあと何年後か、50年後か、それはわからないんですが次の姿になるということもイメージしながら設計をした、そういうようなプロジェクトです。