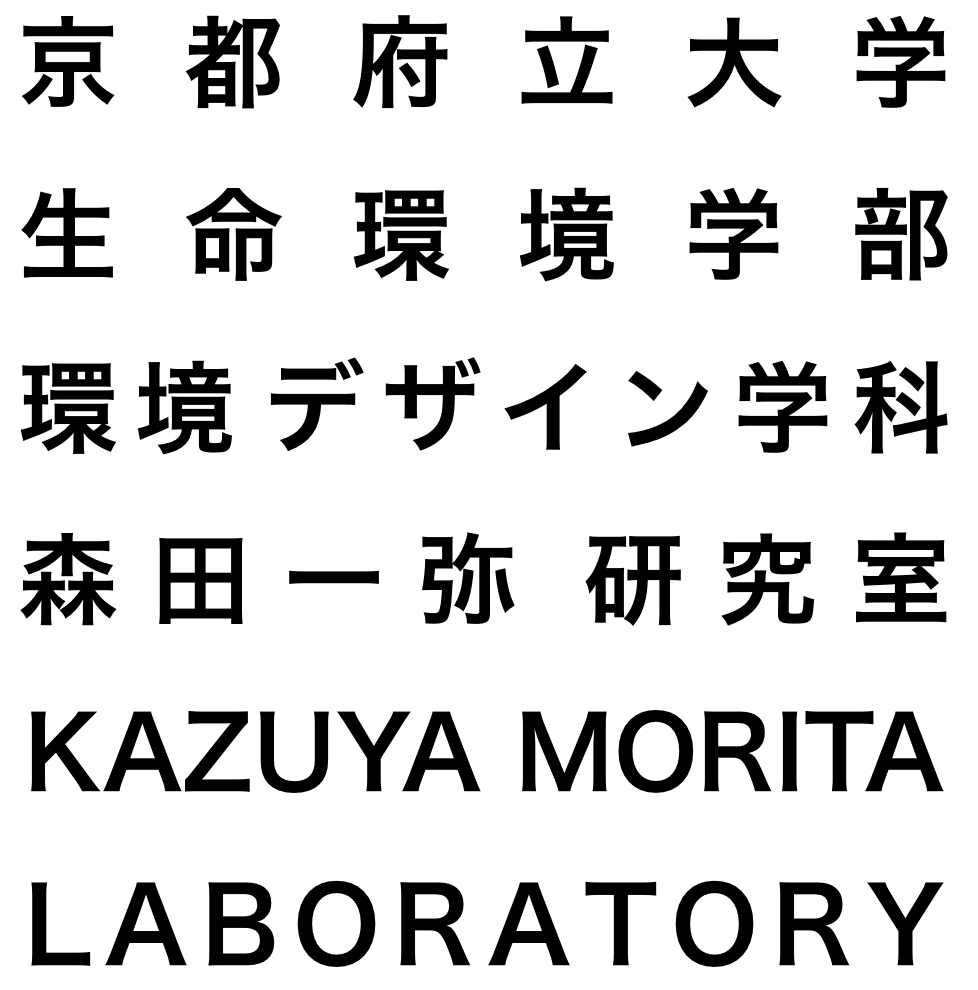質問タイム – 3
森田|
時間がいい時間なりましたね。柳室さんに色々プロジェクトを紹介していただいたり、考え方をご説明いただいたのでちょっと時間取ります。簡単なことでもいいので、皆さん質問していけたらと思います。林さん、いかがですか。

林|
色々なプロジェクトを通して設計者の方との共同を見せていただきましたが、初めて打ち合わせをするタイミングっていうのは設計者の方やプロジェクトによって違うのかなと思っています。柳室さん個人であるとか、構造設計者としてどのタイミングでプロジェクトを一緒に考える機会を作るのが最も楽しめたり、1番発展させられる可能性が残っていたりして、かつ意匠の方針が決まって、そういうのってあるでしょうか。
柳室|
基本的には早い方がいいとは思っています。早ければ早い方がいいよという風に言っていた時期があったので、本当に「土地を見つけました」みたいなところから話をいただくことも逆に増えてきてしまって。
建築家としてその時点で結構やりたいことみたいなものがぼんやりとでもイメージできて、かつ、それが構造的にも特殊な条件の時はよりそうだと思います。例えば、すごい斜面地で構造的にそもそもどういう可能性があるかみたいな。そういう初期アイデアの段階で構造の条件がアイデアにも大きな影響を及ぼす場合は、早ければ早いほどいいと思います。あとは、アイデアに対してどれぐらい建築家として自由度を持たすタイプの人かということにもよるかなと思うんですよ。そもそもあんまり自由度がない人だったら、初期にアイディアもらっても多分そんなに変えることができないので。
今のところは、ある程度1回アイデアを出してもらった方がいいかなと思っています。具体的に図面を書く手前まででいいんですけど。条件整理ってやっぱり大事じゃないですか。 条件によって全然答えが変わるので。アイデアレベルだとこれができるねみたいな話はできるんですが、結局、法律的な話とかいろんな別の物理的じゃないところで決まってくることがあります。ちょっと先生的な言い方ですけど、先にあらゆる条件を整理しておいてもらうと設計のヒントにもなるので、そこは結構欲しいかなという気がします。
あとはやりたいと思っているテーマとかを一応持っていてもらった方がいいかなと。 それがあれば、別にどのタイミングでもいいかなと思います。だからそういう意味では、まだ変更の自由度があって、かつ、条件整備がされているという状態であればどのタイミングでもいいですね。早くても遅くても、そこからまださらに変えられるという状態。「いや、もうお施主さんがこれでオッケー出してしまっているので変えられません」という状態だったら、いくらいいアイデアでもなかなか採用してもらえないので。
森田|
なるほど。他に何かありますか。そちらの方、どうぞ。
参加者|
柳室さん直属の後輩として満田構造計画でスタッフとして働いている稲垣と申します。ふわっとした内容になってしまうんですけれど、所員時代に満田構造計画のスタッフとして、もしくは独立されてから建築家との打ち合わせの中で印象的に残っている言葉などがありましたら、教えていただけたらと思います。

柳室|
それは建築家の言葉と満田さんの言葉のどちらでも?
参加者|
満田さんのプロジェクトの問い方であったり。
柳室|
難しいですね。打ち合わせ中のことではないんですが、満田さんに言われたことで、本当に僕の中ではすごく大事にしていることがあって。「ストレートを投げられるようになるまでカーブ投げるな」という風に言われたことがありました。満田さんはそんなには意識せずに言われたのかもしれない。わかりやすく面白いとか、変わってる、ことを求めがちだと思うんですが、「それより先に正しい答えを出せるのか」みたいなことを言われていて心に残っています。それをやることが間違ってないというか、正攻法を踏まえて出てくる新しさの方がいいんじゃないかと。
森田|
そうしたら、せっかく満田さん来ていただいているので、僕が印象的だった満田さんとの出会いについて。満田さんとは佐々木事務所を辞めて京都に来られたその日ぐらいに、三条のあたりのバーでお会いしてその場で本棚が構造になったプロジェクトの相談をしました。すごく印象的だったのが、満田さんがその頃「だから構造家は楽しい」というブログを書かれていたんですよね。
それを読むと、本当に構造設計やっているのが楽しそうで。「今日こんな打ち合わせをした」「こんなのが大変だった」っていうのを書かれていて。すごく生き生きと構造やっている人が関西に来てくれたなっていうのをすごく感じたんですね。 それで今日は満田さんにブログを書こうと思ったきっかけというか、気持ちだとか。あとは満田さんが佐々木さんからどういうことを感じられたのか、みたいな話を聞かせてもらえたらなと思います。
満田|
構造設計が楽しい、っていうことは自分を保護しているとか勇気づけているとかっていうよりは、あの頃、職業的に構造設計って色々と問題があったんですよ。耐震設計偽装事件があったりして。それと、今みたいなSNSはなくてブログが世の中に出始めた頃で流行りに乗っかっていただけというのもありますが。
そういう言動ってどうしても建築家がリードしてしまう中で、構造家の楽しみはなかなか表に出てきてない状況でした。日常を書くかぐらいの軽い気持ちだったんですが、案外、読者がついてしまってですね。やっぱり「構造設計目指してくれる学生が増えてほしい」みたいな、そういう気持ちを持ちながらやっていましたね。

佐々木さんの話ですが、さっき系譜の話をしてくれていて、確かに僕が佐々木さんから教わって、柳室くんに事務所の中で考えていることを直接伝えてたとかではないし、これとこれが構成する要因だ、みたいな、そんな明確なはっきりしたものはないと思っています。だけれども、そういうなんかしらを受け継いで、それをまた受け継いでという意味で、系譜っていうことがやっぱり正しいという風に思っているし、それを受け継いでいる1人だろうなという風には感じました。
これは褒め言葉なんですが、そういう人が少なくとも関西に2人いるわけです、こうやって京都でね。そのこと自体、僕はやっぱり文化だと。そういうことを一緒に考えてくれる人がいる地域っていうのは、それは、どんな左官職人がいるかみたいなものを含めて、そういうことをするプロフェッショナルがこの地域に色濃くいるかどうかというのは文化だと思います。
設計という意味でも、構造家として活躍する気概を持った人間が、京都クラスの小さな地域の中に複数いるっていうのは、文化が熟成し始めているという風に感じることができました。引き続き、ともに頑張っていきましょう、みたいなことは思えました。もちろんね、まだまだやなと思うところもなくはないですけど、僕もそういうことたくさんありますんで。そういう楽しさをもっと楽しく喋ってほしかったなと。だけどこうやって活躍してくれてる若手が構造の世界に出てきているって、すごい喜ばしい。ぜひ府立大の学生さんも遊びに来てください。昔はバイトさん来てましたし。
参加者|
今日はありがとうございました。 House Aの説明の時に、構造家と施主の距離感みたいな話を少しされていたと思います。施主と直接関わらないからこそ社会的な提案しやすいという話をされていたと思うんですが、社会性っていうものが経済的条件の範囲の中でかなり消極的に行われているような気がしています。それを積極的に打ち出すといったことを考えたことはありますか。
汎用的な構造を用いることで壁の位置を変更できるっていうのはそういうことを行っていると思うんですが、いち構造家としての存在が大きくなればそういった言葉をその構造家の個性としてやられてくるような気がしました。構造家の立ち位置が変化していく、みたいなことを考えられているのか気になります。
柳室|
正直、今のところアイデアレベルというか、社会的意義みたいなことを意識して設計するというところでとどまってると思います。住宅レベルだとなかなか難しいんですが、より公共的なものだと以後の汎用性だとか更新の仕方みたいなところも含めて、トータルでかかるコストが下げられる、みたいなことは、コンペではアイデアに盛り込むこともできると思います。
なので、この事務所に頼むとそこまで考えてくれる、ということは個性として出てくると思います。例えば、クライアントの方から直接「そういった構造事務所を入れて」というオーダーが できるようになるかもしれないとは思います。それは全然あり、 可能性はあるかなと。
森田|
辻先生、いかがですか。東京芸大から来られた先生です。
辻|
昨年度着任したばっかりでまだ新米なんですけども。
まず、感想です。事前に勉強しとかなきゃと思って、〈郭巨山会所〉は建築学会のホームページにある説明を拝見しました。僕みたいに構造を全く素人の人間からすると、普通は必要なスパンに対して必要な柱の断面で詰めていくという考え方があるのですが、そういうのではなくて、町家が持っているその他の寸法を尊重して、それに合わせてその構造を計画していくところがすごく面白いなと思いました。その構造計画自体が町家とか民家、特に民家でしかできない手法だなって思ったんですね。
というのは、奈良女子大学に着任された坂井 禎介さんっていう方がいらっしゃって、民家で使われている見せかけ材としての構造の表現について最近、本(近世民家における意匠操作)を出されてるんです。そこではすごく面白いことが書いてあって。鞍馬にある瀧澤家住宅っていう典型的な京町屋があって実は(郭巨山会所の改修前の)2階の座敷も同じことやっているんですが、普通の町家って半間ピッチで通しで柱をやりますよね。
どうも当時の町家を作った人たちは、例えば座敷とか接客の場所、あるいはちょっと特別な空間に半間ピッチの柱が出るのを嫌がったそうなんです。通り土間の方では半間ピッチの柱が通っているように見えるんですが、座敷に入るとワンスパン飛ばしで大壁にしています。いわゆる片蓋柱(かたふたばしら)って言うんですが、片側だけに見せかけるっていうこともやっていたらしいです。
結論的には「柱に対するこだわりみたいなのが町家は強かった」ということが書かれていました。それを照らし合わせてこの町家の手法を考えると、町家で本来やられていたそういった柱に対するナーバスな気遣いみたいなものが、構造計画で現代化された作品なんだと思って私はすごく感銘を受けました。

質問になるんですが、そうすると今度はあの柱の見え方と、もう1つ独立柱の場合はその断面という感じだと思うんですが、壁がついてるとちりの出をどうするかというもう1つの意匠的なところが出てくると。そこの寸法はこだわりというか。新設の効果、例えば既存の通り土間のところのちりと合わせるとか、そういったところではなにか配慮されたんでしょうか。そこだけ図面を見ていて気になったところで。すごい細かい視点で申し訳ないんですが。
柳室|
具体的には?
辻|
そうですね、そこの辺りで。一応、真壁で仕上げられているんですけど、そこのちりの寸法とか断面のこだわりとか
柳室|
ありがとうございます。柱の寸法の話は結構面白くて、そこまで深く考えていなかったというのが正直なところなんです。柱の寸法を揃えてあげると、あと配置する場所を揃えてあげたら自動的にちりの寸法も一緒になるという考えに至っているので。
実際にはちりの寸法を残す上で構造的に必要な寸法っていうのをこちらから提示してるというのが、正直なところですね。耐力壁で新たに作ってる部分は荒壁パネルという面材を使っているし、元々の壁は土壁を使ってるので、各々に必要なサイズっていうのがあって。それ以上のちりの寸法は意匠の方で決めていただいています。
なので、こちらとしては先に柱の寸法を揃えてあげるっていうことと、例えばこの柱の位置が元々ある柱のすぐ横に来てしまう関係にならないようにしています。今の話だと、壁がくるところっていうのは当然柱の位置が一緒になるので、ちりの寸法を揃えられるのかなと思ったんですが、お答えできていますか。
辻|
すごく面白いなと思って。歴史の視点で見ると、やっぱ町家でしかできない構造で、ちょっと違う類型であってもあまり意味を持たないと思います。
森田|
ありがとうございます。じゃあ、あとお二方どうぞ。
参加者|
構造設計をしていくと、色々と条件を整理したり、自由度を自分の方で決めてあげたりと、様々なことを考えたりすると思うんですけれども、もしすごく自分にその判断が委ねられるようなシチュエーションがあった時、柳室さんは何を大事にしてそこで判断されるのかお聞きしたいです。
柳室|
最初にちょっと話をしたんですが、構造が目的になることはないかなと思っています。なので、自由度が高い中でも何らかのモチベーションは探すんだろうなと思います。優等生的に言うと、もちろん1番コストがかからないようにっていうのがあるかと思うんですが、もしかしたらクライアントによってはコストに制限がないという可能性がある。そうするとそれも根拠になり得ないのですが、いろんなところから探せると思うんですよね。元々建ってた建物がもしあって、その建物から何か引用するとか、 何かしらの根拠を探しに行くと思います。
その時に経済性が重要だってなればそれを条件にすると思いますし、なんとなく気持ち良いみたいなところを押し出してもいいのかなと思います。その時に持っている自分の道具というか。こういうことをやってきたので、次はこれを試したらどうか、みたいなことはあるかもしれない。条件を探してしまうのは性かなと思ってます。根拠を探すことを続けているうちに体の方が慣れてくるというか、根拠がなくても動ける状態になるとは思うんですね。だから、突発的に出る判断を採用してもいいのかなっていう風には思っている感じですかね。
参加者|
小林と申します。本日はお話ありがとうございました。全体の作品をいくつかグループ分けされてお話いただいたと思うんですけど、 聞いていてこれはされてきた作品の分析や分類だと感じています。柳室さん自身はどういう個性があるというか、こういう判断をすることが多い、みたいなことはありますか。
柳室|
逆になにか感じられましたか。それは聞いてみたいと思いますが。
参加者|
そこが難しくて。
柳室|
要するに、あんまりなかったということだと思います。自分で判断して、こういう癖があるとか、こういうことを大事にしてるっていうのを一応まとめたつもりなんですね、テーマとして。もちろん、作品自体はそれらを複合的に持っているので、後で整理してそれぞれで考えていたことをピックアップしたという流れになります。これが自分のスタイルだということも特には強く持っていないっていうのは、正直なところです。
さっき構造家の系譜みたいな話があって、その中ではすごく個性的な方が多いと思うんですよね。構造家の職能としてのフィールドを広げていくために必要だと思うんですが、自分であらかじめ決める個性はあんまり持たないようにしたいとむしろ思っています。
参加者|
ありがとうございます。
柳室|
逆にそれはどういう気持ちから出た質問なんでしょうか。個性があった方がいいんじゃないかっていう?
参加者|
個性は出てしまうものなのかなと思っていて。柳室さんの個性と分類の仕方と、そこに出てくる建築家たちの思考が強く関連しているのかなと感じたので。

柳室|
そういう意味では建築家のことをすごく尊敬しているので、その個性を引き出すようにということを最大限考えてるのかなと思いますね。だから、その建築家がもう少しより理想的な姿になるとしたらどうかをイメージしてるような。別の個性をぶつけるっていう気持ちはあんまりないですね。
結果的に手癖として、例えばハイブリッドなものをやりがちとか、そういうことはあると思います。材料の使い分けとか、いろんな条件を整理したり、組み合わせて、再構築するみたいな操作は好きなので、特徴としてはあるかなと。なんでもかんでもやるという風にはしないようにはしていて、先ほど言ったような、時間軸上の強度があるかとか、空間として気持ち良いかなどは判断根拠になっています。
森田|
ありがとうございました。ちょうど最後の締めとしていい質問でしたね。本日は3時間の予定で、3時間半びっちりお話いただいてありがとうございました。最後に柳室さんに感謝の拍手をよろしくおねがいします。
(会場拍手)